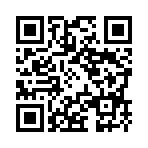› 新しい風の会 › 候補者声明文
› 新しい風の会 › 候補者声明文2009年10月11日
候補者声明文
候補者声明文
1、はじめに
私は「新しい風の会」からの村長選挙への出馬要請を受けましたが、家族や兄弟親族、仲間達、職場の関係者と協議を重ねて、熟慮の結果、あえて村長選挙に立候補することを決意しました。
読谷中学校から読谷高校時代に多くの親友、仲間に出会い、楽しい思い出を沢山作らせてもらいました。特に高校時代は素晴らしい先生方に公私共に指導をしてもらい、部活のバレーボールにおいても最高の指導者に出会いバレーボールを通して、人生最高の喜びを味わい、バレー関係者にも多くの友人ができました。
大学においても教員を目指した学生生活の中で多くの仲間に出会い、素晴らしい尊敬できる教師に出会い、自分のアイデンティティをつくる機会になりました。
ひょんな事から教育・教師から福祉・ソーシャルワーカーの道へ進路が変り、23年間読谷村社会福祉協議会で仕事をさせてもらいました。社会福祉協議会役職員をはじめとする福祉関係者、読谷村役場の関係者、読谷村教育委員会、読谷村青年団協議会、読谷村体育協会、読谷村PTA関係者など多くの方々に育ててもらったと実感しており、非常に感謝しております。
その後、更なる自己向上を志し、沖縄大学で教壇に立たしてもらいましたが、その際も同僚教員を始め、先輩教員、職員、学生達にお世話になると供に、多くの福祉現場、実践者の方々と勉強をさせてもらいました。
23年間社会福祉協議会で地域福祉に携わり、更なる研鑽を積むために大学で教鞭をとらせてもらい、市町村の地域福祉計画策定、職員研修等でも関わらせてもらいました。しかし、社会福祉が極めて実践科学であることから、大学における研究だけでの限界を常々実感していたところです。
私の村長選の出馬決意は、私のこれまでの福祉の研究と実践のすべてを、読谷村に捧げたいという思いからで他意はありません。私を育んでくれた読谷村にお返しをしたいという純粋な気持ちからです。研究者である私が、行政マンとして役にたつかどうかは分かりません。しかし、私の読谷村を思う純粋な熱意が、もし私が村長に選ばれれば、周りの人がきっと私を支えてくれだろうと信じています。
大学で学んだこと、研究した成果をこれからは読谷村で実践に移し、沖縄県内はもちろん、全国に注されるような地域福祉モデルづくり、住民主体の地域福祉の実践に取り組みたいと考えています。
2、考え方
今回、村長選挙に出馬するにあたり、基本的な考え方の一端を申し上げます。村づくりの中心は村民であり、村民主体を基本とします。そのためには行政の情報開示を進めるとともに、住民の代表である議員との関係も緊張関係のある良きパートナーとして、政策についても、常に住民起点で活発に議論をして、具体的政策に反映します。住民懇談会を常に開催し、住民と互いに情報を共有しながら「一人ひとりが輝くむらづくり」のあり方を模索していきます。
基本は「生活者起点での福祉むらづくり」です。
○行政の情報開示は、タイムリーに100%を、基本とします。(個人情報は守秘)
○議会とは、緊張関係のある良きパートナーシップの関係で進めます。
○住民主体を展開するために、住民懇談会を重視します。
村政として対応しなければならない課題は多々ありますが、全てをいっぺんにすることは財政的にも、人材的にも困難なことであると考えます。そこで重点政策を立てて、それにまず取組みたいと考えています。
主な政策項目・重点項目として
1、平和行政を推進します。
2、超高齢社会への対応準備として、福祉政策を重点にします。
3、将来を担う子ども達が夢と希望を育む読谷村にするために、教育政策に力をいれます。
4、持続した地域生活を保障するために、環境政策に力を入れていきます。
5、女性の地位向上の推進を図ります。
6、地産地消を基本とした、農業政策、漁業政策、商業政策を推進します。
7、読谷飛行場の戦後処理及び返還軍用地の跡地利用計画は地主の意向を尊重し、将来発展の拠点として跡地利用を推進します。
8、未加入世帯の解消に向けて取り組みます。
9、読谷村偉人館(屋良朝苗館)の設立を推進します。
10、多選禁止(2期8年まで)を実践します。
上記の項目について、新しい風の会のメンバーや村民と議論を重ねながら具体的実践項目を整理し「マニフェストによる政策提言」として、立候補までには村民に提示していきます。
2009年10月8日 上地武昭
Posted by 運玉儀留 at 23:22